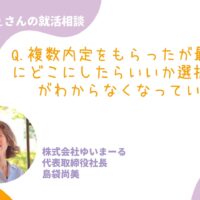<経歴> 映画監督・脚本家。メーカー勤務約10 年の後、2006 年、上野樹里×沢田研二の電器屋親子映画「幸福(しあわせ)のスイッチ」監督・脚本で劇場デビュー。同作品で第16 回日本映画批評家大賞特別女性監督賞、第2 回おおさかシネマフェスティバル脚本賞を受賞。同年末に出産後は脚本業中心となったが、2017 年より監督業復帰。堀田真由主演「36.8℃ サンジュウロクドハチブ」、小芝風花主演「TUNA ガール」、片岡礼子主演短編「あした、授業参観いくから。」、片岡千之助×的場浩司「メンドウな人々」の監督・脚本を担当。
安田真奈 公式サイト https://yasudamana.com/jp/
―映画に興味を持ったのはいつですか?
高校入学前に、森田芳光監督の映画「家族ゲーム」を偶然テレビで観て、「日常生活の設定でも面白い映画は生まれるんだ!」って思ったのが最初ですね。それで高校の映画研究部に入ったんですが、みんなで8ミリ映画をワイワイ撮っていたので、自分の監督作品はありません。大学でも映画サークルに入って、最初は一発ギャグなどを撮ってました(笑)。企画団体にも所属してたので、広告評論家・天野祐吉さんの講演会などの企画もしましたね。映画製作もイベント企画も、みんなで協働する作業ですよね。文化祭もそうですが、「みんなで何かを作りあげる」ということが好きなんです。
―映画監督になろうと思ったのはなぜですか?
大学を卒業してからは、メーカーで働きながら、趣味で自主映画製作を続けて、各地の映画祭に応募しました。受賞を重ねるうちに、監督・脚本業への憧れが強まったんです。そのうち関西テレビの深夜枠で、「オーライ」「ひとしずくの魔法」と、二年連続で映画を撮らせてもらえたんです。放送となると、マイペースな自主製作とは違って、納期という縛りがありますよね。本業が総合職だったことから残業も出張も多く、段々と映画製作との両立が難しいと感じるようになりました。それで9年半勤めた会社を退職して、フリーの監督・脚本業を始めました。
―最初から映像関係の仕事ではなく、メーカーに勤めたのはどんな理由からですか?
モノづくりが好きだったので、メーカーを中心に就職活動をしました。映像業界にも憧れはありましたけど、やっぱり芸大や映像の学部ではないので難しいな、と思って。それから、民放のワイドショーなどで忙殺されて自分の映画が撮れなかったら本末転倒だなと思いました。NHKはドラマが好きだったし、自分の作風と通じる気がしたので受けましたが、残念ながら不採用だったんですよね。
―どんな作風なんですか?
私は、日常の中にドラマを見出すのが好きなんです。「個人の大事件」っていうのかな。爆破や誘拐は、新聞にも載る「社会の大事件」で、映画のネタにもなりやすい。でも、例えば「私が誰かに会って、モメたけど、最終的に人生が明るくなった」という変化があったら、私個人にとっては大事件ですよね。そんな、個々の人生がちょっと変わる瞬間を描きたいんです。もちろん爆破ネタも機会があれば監督しますが(笑)。派手な設定の物語でも、人と人の関わりや、共感、リアリティを大事にしたいですね。
―男性社会の中は大変だった?
家電メーカーでの勤務は 1993年から2002年秋まで。職場は男性中心の雰囲気でした。総合職の女性が親の助けを得ずに育児するのは大変そう…と感じましたね。映画業界も、当時は女性監督は少なかったです。映画製作の中心は東京で、データ通信はまだ発達してませんでした。だから「女性である、大阪(地方)在住である、他の業種の総合職である」この3要素のために、映画祭にいっても “映画を本気でやるつもりはなさそう”と見られがちでしたね。でも途中から、この不利な3要素を活用できると気付きました。
―どうやって3つの不利を活用したんですか?
映画祭って、プロデューサーや製作会社の方と知り合える場なんです。でも、そういう方ってたくさん名刺をもらうから、若手作家を覚えきれないと思うんですよね。そんな中、 「大阪から来ました!」と挨拶すると“毎年大阪からきて、よく受賞してる女性監督がいるな”と覚えてもらえる、と考えました。アポイントを取るのにも活用しましたね。「映画祭ではゆっくりお話しできなかったので、来週上京する際にお訪ねしてよいですか?」と。先方はどんな作品を作りたいのか、自分はどんな作品を描けるのか…などを直接情報交換させていただきました。
―芸大出身ではないとの事ですが、どのように映画界の知り合いを増やしたんですか?
映画祭に行く度に、手裏剣のように名刺を配ってましたね(笑)。プロフィールもよく渡してました。文章よりビジュアルの方が印象に残るので、1枚目はチラシを。2枚目に略歴。3枚目に作品リスト。物語の概要や、監督・脚本・音楽などの自分の役割、受賞歴をまとめたものです。最後の4枚目はインタビュー記事など。興味を持ってくださった方には、自分の映画を収録したビデオテープも渡しましたね。観客の方の「友達に会いたくなった」「心にポッと灯りがともるような映画」といった感想コメントをいれた予告編を、冒頭に必ず収録しました。「お忙しいでしょうから、最初の予告編だけでも見て下さい!」とお願いしてましたね。
―子育てをしているときも監督をされていたんですか?
いいえ。2006年に、上野樹里さんと沢田研二さんの電器屋親子映画「幸福(しあわせ)のスイッチ」で劇場デビューできたんですが、撮影後すぐ懐妊して、その後11年間は脚本業のみになってしまいました。監督業は家をあけることが多いんで、小さい子がいると難しいんですよ。若手監督はどんどん出てくるし、子育てで行動範囲は狭まるし、焦りましたね…。でも逆に、「子どもがいるから」とNHKの児童虐待テーマドラマ「やさしい花」の脚本を書かせてもらえるなど、創作の幅は広がりました。監督復帰できたのは、「また監督をやりたい、こんな作品が撮りたい」と言い続けてたからかなぁ。
―いつ頃、復帰されたんですか?
息子が小5になる頃です。「安田さん、そろそろお子さん大きくなりました?」と、プロデューサーが連絡をくださったんです。「兵庫県加古川市と協働でご当地映画を作りたい。オリジナル脚本を書いて監督もしてほしい。」そうして2017年に監督復帰し、堀田真由さん主演「36.8℃ サンジュウロクドハチブ」を撮影できました。翌2018年も、小芝風花さんが近大マグロを育てる青春映画「TUNAガール」の監督・脚本を担当したんですが、どちらも「関西のノリが分かる、オリジナル脚本が書ける、監督もできる」という3要素が依頼の決め手だったようです。かつて映像業界的には弱みだった「大阪在住」が、ここにきて役立ちました(笑)。
―映画の魅力って何ですか?
映画は「終わらないお祭り」なんですよ。自分の考えたアイデアが、スタッフやキャストの力で120%にも150%にも膨らんでいく、その共同作業のお祭り感があります。さらに、一度作ったら作品として残るので何度でも観られますし、上映のたびに新たな出会いや感動があります。ずっとお祭りが終わらないので、楽しいですね。
―学生へのメッセージをお願いします!
“人生に回り道はない”ってことかな。メーカー勤務は監督・脚本業としては回り道だけど、経験したから描けるコトもあります。女性って、結婚・妊娠・育児といったライフイベントが働き方に影響しがちですよね。やりたいことができなくて、焦る場面が多い。でも、どんな道でも、何か得られるモノがあると思うんです。「回り道だ、無駄だ」と思わず、「何か落ちてへんかなー」とキョロキョロしてたら、収穫があるはず。あとは“やりたいことを言い続ける・発信すること”も大事かな~。応援が得られたりしますしね。自分なりのペースで、やりたいことに向かって頑張ってください!

上野樹里×沢田研二の電器屋親子映画「幸福(しあわせ)のスイッチ」 (c)2006「幸福のスイッチ」製作委員会

育児を経て11年ぶりに監督業復帰「36.8℃ サンジュウロクドハチブ」ロケ現場にて